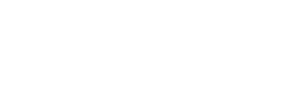第29回
2025.7.1
2025年も折り返し点となる7月を迎えました。今年の関東地方の梅雨は雨量が少ないように思いますが、農作物への影響は大丈夫でしょうか。今夏の水不足を心配しつつそれでも梅雨明けが待ち遠しいこの頃です。
さて、7月は魚介も夏野菜も多種多様になるので天ぷら種には困らない時期だと言えます。改めて自然の恵みに感謝の気持ちが込み上げてきますが、今年は相模湾で良型の泥障烏賊(アオリイカ)が豊漁になっています。なので、今回は泥障烏賊についてお話させていただこうと思います。
泥障烏賊と書いて「アオリイカ」と読みます。なんでもアオリイカの鰭(ひれ)が馬具の「障泥(あおり)」という泥よけに似ていることから名付けられたそうです。
アオリイカは、ヤリイカ科アオリイカ属のイカの一種で、英語ではbigfin reef squidと言います。
とても優雅な泳ぎだとされるアオリイカは、水深50m以浅の藻場や岩礁帯に生息し、日本では北海道南部以南の沿岸に広く分布しています。特に太平洋側の鹿島灘以南、日本海側の福井県以西でよく見られます。漁獲量としては九州・四国の沿岸部で多く水揚げされているようですが、相模湾(神奈川県)でも多く獲れるそうです。胴長は40〜50cmほどで、中には6kgを超えるほど大きくなるものもあるそうです。(ちなみに体長30cmになると1kgを超えるようです。)
アオリイカは、夜行性で夕方から夜にかけて活発に活動します。春から夏にかけて浅場にやってきて、海藻や岩の隙間に卵を産みつけます。産卵を終えたアオリイカのメスはまもなく寿命を迎えます。産卵行動を行わないオスはメスよりも長生きする傾向にありますが、それでも1年半を超えることは稀で、多くは1年以内で寿命を迎えるということです。このように、アオリイカの寿命は1年程度と短い分、成長も早く、卵は約20日で孵化し生まれたばかりの幼体は、夏に小魚や甲殻類などを食べて成長し、秋には300g~800g程度に成長します。そして、冬から春にかけて産卵期を迎え、その一生を終えます。
われわれ人間からすると、アオリイカはその短い一生の中で巧みに環境に適応しながら命をつないでいるのですから感慨深いものがあります…。
食材としてのアオリイカはどうなのかというと、「イカの王様」とも呼ばれるぐらいその濃厚な旨味と甘みが特徴です。身は柔らかく、甘みが強く、刺身や寿司、天ぷら、煮付けなどさまざまな料理に用いられるほど、人気のある食材です。
これまで、イカの養殖は長年困難とされてきましたが、2023年には沖縄科学技術大学院大学(OIST)が世界で初めて「アオリイカの完全養殖」に成功したことが報じられ話題となりました。これは、イカの誕生から繁殖までの全ライフサイクルを人工環境で完結させたという、実に画期的な成果です。
その理由は:
- 水槽内での激突事故:イカは目が横にあり、進行方向が見えにくいため壁にぶつかりやすい。
- 水温に敏感:アオリイカは20℃を下回ると餌を食べなくなり、15℃以下で死んでしまうことも。
- 生き餌への依存:生まれたばかりの稚イカは生きた餌しか食べず、コストと手間がかかる。
OISTの研究チームは、これらの課題を以下の方法で克服しました:
- 自然海水のかけ流し方式:人工海水ではなく、海から直接引いた自然の海水を使用し、ストレスを軽減。
- 水槽サイズの段階的調整:成長に合わせて水槽を広げ、共食いを防止。
- 餌の工夫:早期から冷凍餌に慣れさせることで、生き餌への依存を減らしコスト削減に成功。
- データ駆動の管理**:給餌時間や個体数、水槽の大きさなどを細かく調整し、最適な環境を維持。
国産のアオリイカは漁獲量が少なく、「高級食材」として扱われているので、この技術が普及すれば、アオリイカの安定供給が見込まれ今よりも安価で口にできるようになるかも知れませんね。
今夏の相模湾はアオリイカが豊漁で2.5kgもある大物が水揚げされています。ぜひ葉むらで旬の泥障烏賊を味わってみてください。
(次回につづく‥‥‥)
(文:立)
注釈:文中で取り扱っているデータ等については、Gemini・Bing AI(Chat-GPT4搭載)との対話及びネット情報、文献等からの筆者独自の分析によるものです。