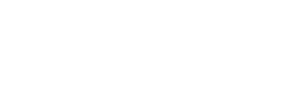第28回
2025.6.3
深緑の季節となりました。樹々の葉も大きく成長し植物の生命力の強さが感じらる今日この頃です。
生命力の強さといえば、これから旬を迎える「鱧」(ハモ)が頭に思い浮かびます。京都の夏の風物詩として、祇園祭の頃には鱧がよく食べられ、鱧は京料理に欠かせない食材とされていますが、昔から鱧だけは京都まで生きたまま運ぶことが出来たぐらい生命力が強い魚だそうです。
「京都の鱧は山で獲れる」
これは魚屋が京都へ運ぶ途中に籠を落として鱧が散乱、拾い忘れた鱧を地元の農民が見つけたことからそう言われたという言い伝えがあります。
そんな鱧ですが、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?その見た目からうなぎや穴子を思い浮かべたり、白身魚、高級魚であるといった感じでしょうか…。
鱧は主に西日本で水揚げされ、特に兵庫県・徳島県が有名です。
ハモの旬は6月から7月にかけて。この時期鱧は産卵を控え脂がのって身が締まり、とても美味しくなるためです。「梅雨の雨を飲んで旨くなる」と言われるほど、夏の味覚として人気がある魚です。また、晩秋にもう一度旬を迎えるという説もあり、これは晩秋 (10月~11月頃)、産卵後に栄養を蓄え、脂がのってくるため、再び旬を迎えると考えられており、この時期のハモは、「金ハモ」や「落ちハモ」と呼ばれ、独特の風味があるそうです。
鱧は漁場や餌の質、水温・水質などによって品質が左右されるので、島の南部や沼島近海といった地形の特徴から潮流が速く、すみかとなる海底の水が常に新鮮でよどみがなく、 甲殻類などの餌が豊富な場所で獲れる鱧は、特に品質が高いとされています。例えば、淡路島産の鱧は、ブランド化されていて、品質を保証する商品として高値で取引されているようです。鱧は、特定の地域でしか獲れないため、その希少性から価格に影響しているようです。
さらに、鱧は身に小骨がびっしりと密集しており、それを1mm間隔に皮を切り離さないように切り込みを入れて小骨を断つ「骨切り」という高度な調理技術が必要になります。このような高度な調理技術も相まって高級食材となるのです。鱧が高級である理由がお分かりいただけたのではないでしょうか。
鱧は、栄養価も高く、ビタミンB1やビタミンB2、ビタミンB6などのビタミン類をはじめ、カルシウムやリン、マグネシウムなどといったミネラルも豊富に含んでいます。ビタミンB1は糖質の代謝を助け、疲労回復や細胞の新陳代謝促進を促し、ビタミンB2は皮膚や粘膜の機能維持や成長に役立ちそうですから、体にも良い食材と言えそうです。
鱧はお寿司や天ぷら、蒲焼、湯引きして梅肉酢や三杯酢で食べる鱧ちりなど様々な調理法で食することができます。ぜひ葉むらで旬の鱧を味わってみてください。(次回につづく‥‥‥)
(文:立)
注釈:文中で取り扱っているデータ等については、Gemini・Bing AI(Chat-GPT4搭載)との対話及びネット情報、文献等からの筆者独自の分析によるものです。