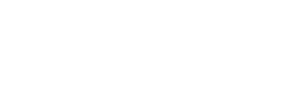第27回
2025.5.2

清々しい新緑の季節を迎えました。草花がより一層色鮮やかに見える季節で心が明るくなります。天ぷら種も此の時期ならではの山菜や魚介が届くようになってきました。今回は、春から初夏にかけて旬を迎える琵琶湖の稚鮎についてお話ししたいと思います。
「鮎」と聞くと、「鵜飼」を想像する方も少なくないのではないでしょうか。長良川で鮎を捕る有名な漁法の「鵜飼」はあまりにも有名です。鵜匠が海鵜を操り、川に潜る鮎を捕まえる伝統的な漁法で、夏場の観光客に人気がありますが、葉むらで扱う鮎はそのような鮎とは異なり、「琵琶湖の稚鮎」です。「小鮎」と呼ばれる種類のものです。
琵琶湖の稚鮎は、小鮎(コアユ)と呼ばれる体長10cmほどの琵琶湖で育つアユで、これでもって立派な成魚なんです。串に刺して炭火で焼く「鮎の塩焼き」のアユは体長がその倍以上あるので、琵琶湖の小鮎を見ると、まだ「稚鮎」かという印象を持たれる方が少なくないかもしれません。
よく鮎は「清流の女王」とも呼ばれることから、ずっと川で一生を終える川魚のイメージが強いかもしれませんが、一生の間に海と淡水域を往復する魚で、淡水で産卵し海で成長するというパターンを持つ淡水性両側回遊魚と呼ばれるものです。遡河回遊魚とも呼ばれます。鮭をイメージするとよく分かるかと思います。これが一般的な鮎です。
しかし琵琶湖のコアユは、仔稚魚期に海には下らず、琵琶湖を海の代わりとして利用していると考えられています。中には琵琶湖に流入する河川を遡上して、他地域で見られる通常の鮎のようにオオアユに成長するものもいるそうですが、琵琶湖内にとどまって大きく成長しないコアユが「琵琶湖の稚鮎」もしくは「小鮎」と呼ばれるものです。
春は追いさで網、夏は沖すくい網、また早春から始まる小糸網など、様々な漁法で漁獲され、天ぷら以外にも佃煮や塩焼き、天ぷら、マリネ、南蛮漬けなど、丸ごと食べられるのが特徴で、様々な料理で楽しめる食材です。うろこが細かく滑らかで、皮や骨が柔らかく、しっとりとした食感と独特のほろ苦さや香りが特徴です。葉むらで旬の琵琶湖の稚鮎の天ぷらを味わってみてください。(次回につづく‥‥‥)
(文:立)
注釈:文中で取り扱っているデータ等については、Gemini・Bing AI(Chat-GPT4搭載)との対話及びネット情報、文献等からの筆者独自の分析によるものです。