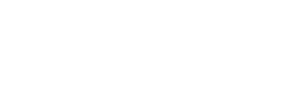第33回
2025.11.1
11月を迎えました。街中の公園や緑地では金木犀の香りがしたと思えば、道端にどんぐりの山ができ、銀杏の実はすでに落ち、気温が下がって空気は早冬(ふゆ)の気配を感じられる季節になりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。長く居座り続けた夏のせい!?で、急ぎ足で秋が通り過ぎてゆくのを実感している今日この頃です。
さて、季節の食材はまだまだ秋本番で、旬の食材が目白押しです。今年は入荷できそうにない貴重な天ぷらタネである「沙魚」(ハゼ)を取り上げてお話させていただこうと思います。
日本人なら多くの人が、沙魚(ハゼ)という魚の名前には聞き覚えがあるのではないでしょうか。ハゼは、主に汽水域を中心に、淡水、海水と幅広く生息します。 ハゼはスズキ目ハゼ亜目(ハゼ科など)に属する硬骨魚の総称で、ハゼ科には約2000種(日本では600種以上)いるとされています。
全長が約20センチメートルで、体は細長く、目が頭の上部に位置し、多くの種で左右の腹びれが癒合し、吸盤のようになっています。
ハゼという名前の由来は諸説あるようですが、勢いよく跳ねる様子から「はねる」が語源という説や、俊敏に水中を「馳せる」からという説、漢字の「沙魚」は、「水中の浅瀬にいる魚」、または「水中の砂地に棲む魚」から来ているという説もあります。「沙魚」や「鯊」と漢字で書きます。
かつて、東京湾などで「江戸前」の代表的な天ぷら種として重宝されていたハゼは「真沙魚」(マハゼ)です。なので、今でも天ぷらに使われるハゼはマハゼです。
では、マハゼの一生とはどのようなものでしょうか。
マハゼの稚魚たちは春に孵化して川を遡り、浅い場所に集まり、夏に若いハゼとなって河口や運河を下っていき、秋になると再び海に集まります。そして冬には汽水域の海底に巣穴を掘って卵を産みますが、ほとんどのマハゼは、メスは産卵後すぐに、オスは卵の孵化を見守った後に一生を終えてしまうのだそうです。年魚には、マハゼはアユと同じく年魚です。年魚とは、生後1年以内に産卵して死んでしまう魚のことをいいます。マハゼは雑食性がとても強く、小さな時には、動物プランクトンなど水中に漂っている小さな生物を食べていますが、成長するにつれ、砂に潜っているゴカイや小型のエビやカニ、小魚といったものを食べるようになるそうです。
マハゼは、とてもポピュラーな魚で、食用としても親しまれ、江戸前の天ぷら種としても欠かせない魚でした。ところが最近では獲れる場所や数が減ってしまい、大衆魚とは呼べなくなっているのです。1970年代までは、まだ東京湾で漁業者が生業とするほどたくさんのマハゼが漁獲されていたそうですが、その後、高度成長期における河川の水質悪化や生息域の縮小等によりマハゼも減少してしまったということです。
ただでさえ、食用としては痛むのが早く、なかなか市場には出回らないものが、漁獲高の減少により大衆魚とは呼べなくなってしまいました。その結果、高級魚として取り扱われているというわけです。近年では、行政や住民など様々な主体が回復に向けての活動を各地で進めているそうなので、またマハゼの天ぷらを気軽に食せる日が来るかもしれませんね。
マハゼは釣りの初心者向けの魚の代表といってもよいくらい、よく釣れる魚だそうで、江戸時代にはすでに多くの人がハゼ釣りを楽しんでいたようです。なので道具に凝る人も多くなり、釣り具の研鑽がすすんで伝統工芸品の「江戸和竿」(えどわさお)の基礎が育まれたといわれています。
※江戸和竿は江戸時代の天明年間に発展した継竿の技術で、1788年(天明8年)に江戸上野広徳寺前に創業した泰地屋東作が元祖です。その後東作の弟子が独立していくことで現在の系譜に繋がっています。
ハゼ釣りと思われる浮世絵も数多く残されており、描かれたその様子から庶民の間で気軽にそして身近な存在であったことが窺い知れます。
昭和に入ってからも「だれにでも釣れる魚」としてハゼ釣りはブームとなり、今でも多くの人がハゼ釣りを楽しんでいました。
春に生まれたマハゼは、夏から秋にかけては10~20cm程度に大きく成長するため、この時期は餌をたくさん食べるので、釣り人にとってもベストシーズンで9月の彼岸ごろには、江戸前の釣り船が一斉に船を出していたそうです。
かの有名な俳諧師・松尾芭蕉。その高弟だった服部嵐雪(はっとり らんせつ)(承応3年[1654年] – 宝永4年[1707年])が詠んだ句の中に、「鯊(はぜ)つるや 水村山郭 酒旗の風」という句もあります。
余暇にハゼ釣りをして楽しんで、釣果はそのまま美味しい天ぷらとしてお腹を満たしてくれる。そんな古き良き時代が再び訪れるといいなぁと思っています。そんな機会が訪れることを期待しつつ「葉むらの天ぷら」を味わいながら、ご主人としばし「ハゼ談義」を味わってみてはいかがでしょうか。(次回につづく‥‥‥)
(文:立)
注釈:文中で取り扱っているデータ等については、Gemini・Bing AI(Chat-GPT4搭載)との対話及びネット情報、文献等からの筆者独自の分析によるものです。