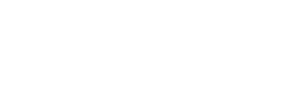第31回
2025.9.1
9月を迎えましたがまだまだ「真夏」の陽気が続いています。今夏は本当に「猛暑の夏」に日本列島全体が覆われた感じがしますが、酷暑はまだもうしばらく続きそうですから体調管理には十分留意されてください。
さて、暑さは衰えずとも自然界の季節は確実に移り変わっています。今回は秋ならではの旬の食材として「栗」をピックアップしてお話させていただこうと思います。
秋が旬の木になる果物の一つ、庶民には昔から身近な秋の味覚である「栗」ですが、美味しさだけでなく、炭水化物、ビタミンC、カリウムなどが豊富に含まれる栄養価の高い食材です。
栗を食する歴史は古く、青森県の三内丸山遺跡や長野県の遺跡では、1万年前の食用栗が出土していることから、日本では今から9000年以上前の縄文時代から食べられていることがわかっています。縄文時代の人々にとって栗は貴重な主食であり、安定的な食料として利用され、中には大粒の栗も確認されていることから、栗の栽培技術も持っていたと考えられています。
栗は「久利」と記され、万葉集や古事記にも登場します。食糧や菓子のほか、栗の木は材質が固く、腐りにくいため、祭祀用の建物や住居、道具、燃料など、建築材や資材としても利用されていました。 線路の枕木は現在ではPC枕木(コンクリート製)ですが、明治時代には、線路の枕木として栗の木がよく使われ、栗は日本の近代化に大きく貢献したということです。
さて、そんな昔から愛されている栗ですが、私たちが食べている果肉の部分が実は「種」だということを知っていますか。栗の木は雌雄異花で、雌花と雄花があり、受精した雌花が実をつけます。もともと雌花にはトゲがあり、これが実をつけたときにイガになります。イガは他の果物でいう皮に当たり、その中にある栗が果肉と種です。なので、一般的に栗の皮だと思われている鬼皮が他の果物の果肉にあたる部分で、表面の皮(鬼皮)だけむいた渋皮つきのものが種ということになります。
雌花にあるトゲの部分は総苞(そうほう)といい、その中には将来、種となる子房が、通常3つずつ入っています。受精すると総苞はイガになり、子房が栗となります。そのため、一般的な品種では1つのイガの中に3個の「3つ栗」です。ただ、茨城県のブランド栗「飯沼栗」のように、栽培技術によって、1つのイガに栗が1つだけ入った大粒の栗も生産されているということです。
栗の主要産地は、全国で第1位の茨城県(笠間市など)、第2位の熊本県(山鹿市など)、第3位の愛媛県(大洲市や伊予市など)、第4位の岐阜県(中津川など)、第5位の埼玉県となっています。
ブランド栗としては京都府の「丹波栗」や長野県の「小布施栗」、愛媛県の「中山栗」が有名で、中でも中山栗は日本三大栗の一つで、江戸時代には将軍徳川家光にも献上され喜ばれたそうです。
また、丹波地域で採れる大粒の栗“丹波栗”ですが、そもそも全国に知られるようになったのは江戸時代の参勤交代を通じて全国に広まったとされています。
そんなシンプルに調理して食べても、スウィーツにして食べても美味しい栗ですが、天ぷらにして食べても、これまた絶品なんです!
是非、葉むらで秋の味覚「栗」の天ぷらに舌鼓を打ってみてください。
(次回につづく‥‥‥)
(文:立)
注釈:文中で取り扱っているデータ等については、Gemini・Bing AI(Chat-GPT4搭載)との対話及びネット情報、文献等からの筆者独自の分析によるものです。