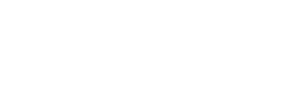第30回
2025.8.1
暑中お見舞い申し上げます。
8月を迎えましたが、連日猛暑続きで身体が悲鳴をあげそうですが皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私が子どもの頃には午前中に気温が30度を超えるなどという日はなかったように思いますが、今夏は朝起きて午前8時、9時にはもう既に30度超えという日が少なくありません。
水分補給など熱中症対策に留意してお過ごしください。
さて、今月はまさに旬の食材「鮑(アワビ)」についてお話させていただこうと思います。
皆さんはアワビについてどうのような印象をお持ちでしょうか?
私の場合は、家庭の食卓には上らないという高級食材のイメージがあるのですが、皆さんはどうでしょうか。
そんなアワビは、見た目は平たい一枚貝のようですが、実は渦巻き構造を持つ「巻貝」でミミガイ科に属しています。生息地は北海道南部から九州沿岸、朝鮮半島、中国北部などの岩礁地帯で、コンブ、ワカメ、アラメなどの海藻類が主な餌です。習性は夜行性で昼間は岩陰に隠れて過ごします。
アワビは世界中に約100種、日本には10種が分布しており、 そのうち日本で一般的にアワビと呼ばれる食用のものは、クロアワビ、エゾアワビ、マダカアワビ、メカイアワビの4種類です。そして市場で流通している活アワビのほとんどは、クロアワビとエゾアワビの2種類だそうです。
クロアワビの旬は夏で、千葉県南房総や三重県、和歌山県、長崎県五島列島、伊豆半島など、太平洋沿岸や暖流の影響を受ける外洋に面した地域でも漁獲されますが、なんといっても岩手県三陸海岸が、クロアワビの主要産地として知られています。
もうひとつのエゾアワビの旬は冬で、こちらも岩手県三陸海岸が主要産地として最も高い漁獲高を誇っていて漁獲量の20%を占めています。次いで北海道、宮城県と続きます。エゾアワビは寒い海で育つため、身が締まり旨味が凝縮されています。
アワビは、生でも、煮ても、焼いて食べても美味しい食材です。
もちろん揚げて食べても納得のいく旨さを味わえます。
そんな多様な調理方法で私たちの舌を楽しませてくれるアワビですが、その万能ぶりは単なる高級食材という範疇にとどまらず、歴史・信仰・縁起・外交までを担ってきた特別な存在といえます。
まず、縄文時代の貝塚からアワビの殻が出土しており、その頃からすでに食用・器として利用されていた痕跡がうかがえます。
万葉集にも登場することから、アワビが古くから珍重されていたことがわかります。
万葉集
第11巻 2798番歌:
伊勢乃白水郎之 朝魚夕菜尓 潜云 鰒貝之 獨念荷指天作者: 作者不詳
訓読: 伊勢の海人の朝な夕なに潜くといふ鰒の貝の片思にして
訳: 伊勢の海女が朝な夕なに潜ってとるというアワビ。そのアワビのように片思いのままでいる。第18巻 4103番歌:
於伎都之麻 伊由伎和多里弖 可豆<久>知布 安波妣多麻母我 都々美弖夜良牟作者 大伴家持
訓読: 沖つ島い行き渡りて潜くちふ鰒玉もが包みて遣らむ
訳: 沖の島に渡って海中に潜ってとるという真珠を土産に包んで贈ろう。参照先:万葉集ナビ
アワビは二枚の貝を持って生まれますが、生後15日ほどで透き通った片方の稚貝を捨ててしまうため「磯のあわびの片思い」といわれるそうです。
平安時代に醍醐天皇の命により、役人の行政マニュアルとして編纂された『延喜式』の中に、鮑が天皇の食膳や祭祀に欠かせない食材として記録されており、特別な場面での使用が定められていました。鮨鰒(すしあわび)という発酵保存食も存在し、米飯とともに加工されていたこともわかっています。
古くは朝廷への貢物、お祝いの食用として重宝され、また干し鮑にして保存しました。室町時代、アワビの肉を叩いて薄い干し物にし、さらに末広に切って重ねたものが、熨斗(のし)の語源であり、贈答文化の象徴として今も使われています。
また、武将たちは出陣前に「三献の儀」で打ち鮑・勝ち栗・昆布を食し、勝利を祈願しました。「打ち・勝ち・喜ぶ」の語呂合わせが込められています。織田信長、徳川家康、武田信玄などもアワビを好んだとされ、権力者の食卓に並ぶ高級品でした。
山梨県では、海のない地域にもかかわらず「鮑の煮貝」が名産品に。これは駿河(静岡)で獲れたアワビを醤油漬けにして馬で運び、保存性と味を両立させた知恵の産物です。
明治時代には、南房総の漁師たちがカリフォルニアに渡って鮑漁を展開し、アメリカで鮑ステーキや缶詰が人気となり、食文化に革命を起こしました。日系人コミュニティの中で、アワビは日米交流の架け橋としても機能したそうです。
伊勢神宮などでは、今でも神饌(しんせん)としてアワビが奉納されることがあるそうです。
乱文になってしまいましたが、鮑(あわび)に関する歴史と文化は、日本の食文化の中でも格式と縁起を重んじる伝統が色濃く反映されていることがよく分かります。
古代から現代まで伝わる「鮑(アワビ)」が、実は「神に捧げる食材」「武士の勝利祈願」「贈答の象徴」として扱われてきたということを理解すると、次回アワビをいただく際にはより高尚な味を感じられるかもしれません。是非、葉むらでそのアワビを堪能してみてください。
(次回につづく‥‥‥)
(文:立)
注釈:文中で取り扱っているデータ等については、Gemini・Bing AI(Chat-GPT4搭載)との対話及びネット情報、文献等からの筆者独自の分析によるものです。